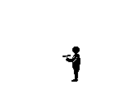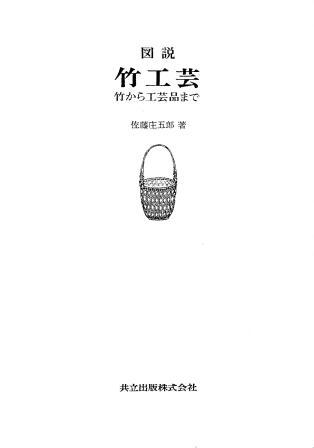「図説 竹工芸」の「乾式脂抜き(火晒し)P37」には次のように記述されています。
火にあぶり、十分蝋脂質を滲み出させて直ちに布片で拭き取る方法。竹を回して焦がさぬよう且つムラのないように熱して、黒いかすを残さないように、手早く丁寧に拭き取る。
加熱によって蒸気圧となった組織中の水分が、内皮層に妨げられて外部へ蝋脂質を伴ってふきでる。それが溶けている間に手早く拭き去る。布片は竹の脂の染込んだものが光沢が出るという。
竹は伐採後、風通しの良い所に1〜3ヶ月陰干しし、水分がおおかた蒸発したものに行うのが最も良く、すぐ良い色に仕上がる。 乾式法を行うとおおむね硬度が増し可撓性が減少する。 脂抜きは入梅前(4月)に終わるのがよい。
写真1 伐採後2ヶ月経過の真竹を台所のガスコンロで火あぶりしたものです。水分がかなり残っている状態ですので均一な色合いになっていません。
写真2 伐採後3週間経過の孟宗竹です。乾燥は井桁に組み南側の部屋で行いました。脂抜きのつもりで火あぶりしたのですが、水分が多すぎて端が焦げ色合いも良くありません。脂分は抜けたようですが、割ってみると内部には水分がいっぱいです。
写真3 伐採後12ヶ月経過の孟宗竹を脂抜きしているところです。手前の白い粉が噴いている部分は未処理、光沢のある部分が脂抜きした部分です。
写真4 同上の処理を施した状態の竹材です。
ガスコンロでの火あぶりは、弱火にし約10〜20秒(厚さによる)かざし、脂分が溶けて光っているうちにぼろきれで拭き取ります。温度が下がりタール状に固まった部分は再加熱し、拭き取りを繰り返します。脂分を吸込んだ部分の布は固まります。
失敗体験
火あぶりする時の竹材の状態は、40mm程度に割った長い状態をお薦めします。
150mm程度の羽根の長さに切ったものは手で掴む部分が少なく「あーちっち!」の憂き目に会います。長いままのほうが拭き取り作業が一挙に出来、結果的には効率的でした。数枚の羽根材でしたら所用の寸法に切断後でも構いませんね。
乾燥を速めようと内側の肉部分を落とし平に削り終えた羽根材用意しました。これを加熱すると、水分が内側に出ることにより、折角平らに削った面が膨らみ再加工したこともあります。
「竹工芸」の記述の「組織中の水分が、内皮層に妨げられて外部へ」の、「内皮層」を取り除いた失敗例ですね。 |