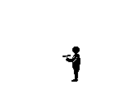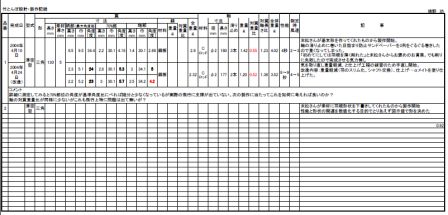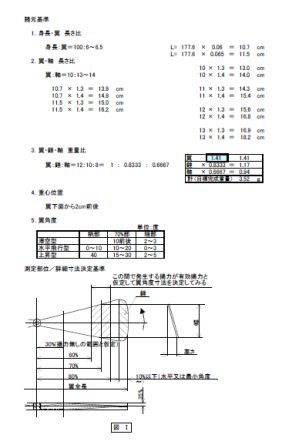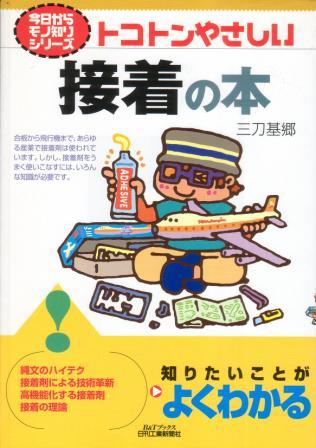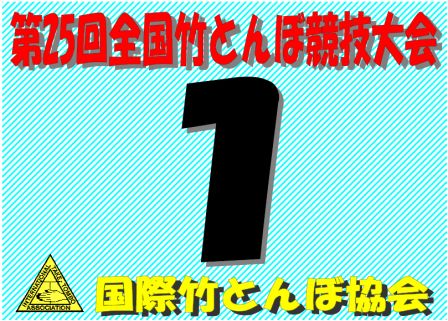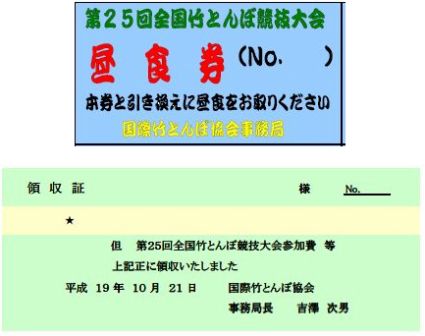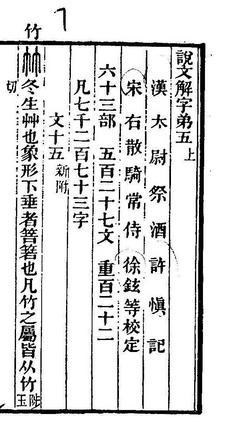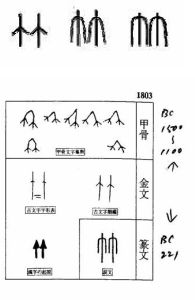�@���̃J�e�S���[�ł́A�|�Ƃ�ڂ�ʂ��Ă̖ʔ����������ς��L�^���Ă��܂����A���ߒ��ł̊y������ꂵ�݂��u�����鉻�v����Ă��܂���B
���ꂩ��́u�J�e�S���[�v�Ɂu�|�Ƃ�ڂƂ̋ꓬ�v�̗L�l���I���܂��B��肭����������������s������Љ�A���ꂩ��u�|�Ƃ�ځv�����n�߂悤�Ƃ���F����ɉ�蓹�����Ȃ��ł��ގQ�l��ƂȂ�K���ł��B
�@�L�q������e��\�����@��chikusui�̓ƒf�ł�����L�ۂ݂ɂ��������Ă��������B�Ԉ���Ă��邱�Ƃ��݂����琥��R�����g�����������B
�@��G�c�ɂ͎��̏��ԂŋL�q���悤�Ǝv���܂����A���Ԃ��ς������A�����ɂ���邱�Ƃ�����Ǝv���܂������e�͂̒��B�܂��A���e���鎟���͂܂�Ōv��I�ł͂���܂���̂ō��𐘂��Ă��҂����������B
�@�P�D���|�̗{�������J�r�������č������I
�@�Q�D�|�̐���A������������������|�̐�
�@�R�D�H���ނ̍��������f���łȂ��|�̑@��
�@�S�D���^�̂��낢�륥���f�U�C������������A�ł�����H
�@�T�D�r�����̕��@�����V�����g���[�̔�����
�@�U�D���^�̐�o�������v�������ʓ���̊��p
�@�V�D�H���̍����������X���̐i��
�@�W�D�o�����X�̎���
�@�X�D���̍��������ڂ̐��x�Ƀr�b�N���I
�P�O�D�g�ݗ��ĕ�
�P�P�D�����
�P�Q�D��ԗ��_�i�������ł��j
�@
�@�ʐ^�P�@�Џ@�|�̗�
�@�ʐ^�Q�@���̒���̓������{��
�@�ʐ^�R�@���^�̐؏o��
�@�ʐ^�S�@�o���オ�� |