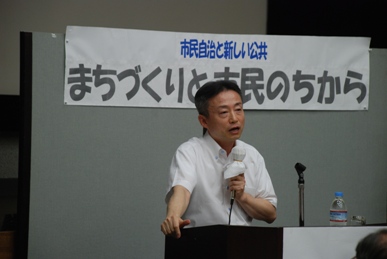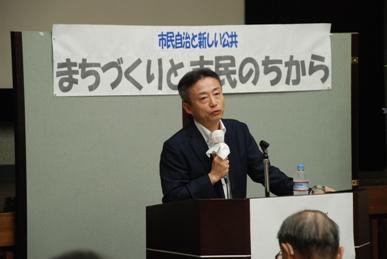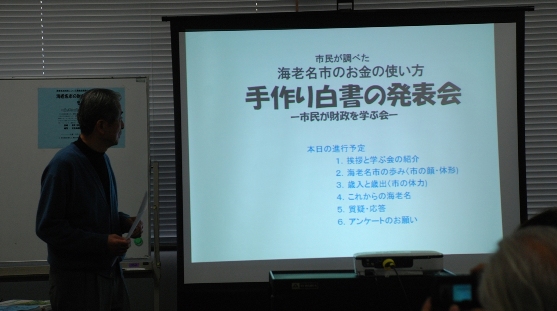「さむかわ市民オンブズマン」山蔦紀一さんからBCC報告が届いていますので転載します。
昨日、ひらつか自治体財政研究会と湘南NPO サポートセンター主催で行われた、講演を聞きました。 於:平塚市図書館、参加80名ほど 要旨を、私なりにまとめましたので、お送りします。
「協働」と言う言葉だけが、世間を飛び交っている昨今ですが、この意味を的確に解析していただいたと思います。
また、我孫子市(人口13万人)は、補助金の効率化のため、3年に一回、一旦全部廃止し(ゼロにし)、申請を受付し直すことによって、リフレッシュするとのこと。 既得権やエコヒイキをなくすため、市民を入れた審査会が、補助先と金額を査定するとのこと。当然市長も口を出さないとのこと。 寒川町でも採用できると思いました。何年も(効果不明のまま)惰性で出ている補助金があり、一方で必要な補助金が出ていないというのが、寒川の現状ではないでしょうか?
議会と行政のあり方についても、北海道栗山町の例を出して、政策で競争するような「緊張感」と「議会への住民参加」が不可欠だ、と強調されていました。 参考になれば幸いです。
福嶋浩彦消費者庁長官(前我孫子市長)の講演要旨 H24.6.23 於:平塚市立図書館 要旨文責:さむかわ市民オンブズマン 山蔦紀一
1.「住民提案型協働事業」は、本当の「協働」ではない
1)協働は、行政が「許可」するものではない。
・安上がりになることが「協働」の目的ではない。そうなら景気が良くなったら「協働」しないことになる。
・行政側が安易に「協働」と言い、住民も補助金が「貰える」から「協働」と言う例が実に多い。市民が行政の下請けであってはいけない。
・「協働」は「何とかしたい」という「市民の強い思い」がスタート点だが、行政が間に立つのではなく、市 民自身が合意を作る力(優先順位を決める力)を持つことが不可欠だと思っている。
2)住民主権は、住民が「行政の上に立つ」という意味である。
・行政は市民の「しもべ」である。国と違い、市長も議員(議会)も、法律上、市民が罷免できる。これが地 方自治の基本である。ただ、行政の効率化を狙って「事業者(NPOなど)」に委託する場合は、競争原 理を入れて決めたとしても、「事業者と行政は対等」であるべき。
・「協働」にはこの上下関係と対等関係の2つの面があるが、協働の受益者は行政ではなく「市民」だ。
3)行政には(コストを含め)政策実施のベストの方法(直営か委託)を選定する能力が求められる。我孫 子市で1100の事業の仕様書(レビュー)を公開し受託の公募を行ったことがある。これによって、ベス トの方法を探すことができたが、「新しい公共」の担い手も育って行くと期待した。
市民から遊離して、勝手に行政が公共を仕切る、のが一番いけない
2.栗山町議会は自ら勉強して、町長提出の「財政健全化計画案」を破棄し差し替えた。・議会と行政の間に、(市民のために競争するという)「緊張感」がなければならない。・議会に「決定機関だ」という自覚が薄い。議員が、「議案を審査する」、「役所に要求する」また「支持者へ の利益誘導をする」例が多いのが現状だ。もっとオープンにして議会への住民参加を促すべきだ。
3.補助金を、3年に一回、リフレッシュした。
・既得権・エコヒイキをなくすため、3年に一回全部廃止し、市民を入れた審査会で新たな補助先を決め た。市長は口を出さない。市長選で支持してくれた団体への補助も一旦ズバーと切った。こうしないとこ のやり方は続かないし、住民は「公平」になったと思わない。職員採用も同じように審査会で決めた。
・イラクに派遣された自衛隊隊長と人質になった民間人を呼んで、「平和維持への補助金のありかた」の 公開議論をした。反戦団体の猛抗議があったが、「毛嫌いせずに議論することが大切」と説得した。
・予算編成過程も、4段階で市民にオープンにした。「なぜこの予算を削ったのか!」と言われ激しく役所と 議論になったこともある。行政が対立を避けると、結局、市民の参画も行政への信頼度も上がらない。
4.住民投票を行う条件をあらかじめ定めておく条例、を制定した(全国で2番目)。・行政に「住民の日常的な監視があるのが当然」と考え、迅速に住民投票ができるようにした。(以上)
(注)この講演会は市民活動センターと平塚のオンブズマン組織の共催。平塚市長も来場していました。