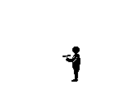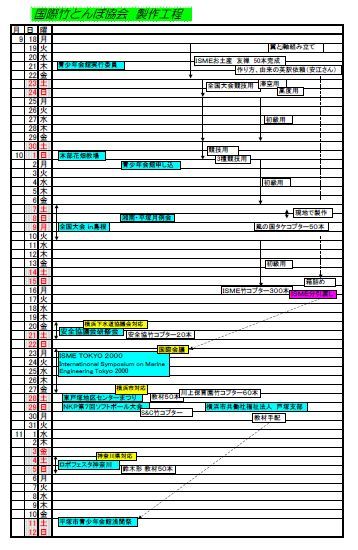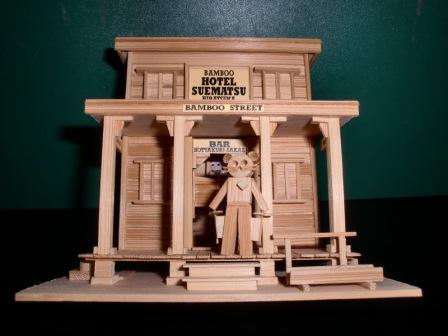竹とんぼ作りを紹介しお勧めするのは、大掛かりな設備を必要としないからです。丸竹を割る、切る、鉋を掛ける等の素材成形作業は庭仕事となりますが、竹とんぼ工作の大半は小さなスペースで出来ることです。羽材を小型万力に固定し外形を切出すこと、最も神経を使う軸孔開け、ヤスリ仕上げの作業など卓上で可能です。家族が寝静まった夜中に、背中を丸め工作に没頭する姿を想像して見てください。
マンション住まいの方、自宅に工房をお持ちの方、猫の額で工作する方など居住環境は異なりますが、作業内容と作業場所を工夫し独自の愉しみ方をしています。例会で紹介されるアイディアを持ち帰り、自分なりのスタイルに変更し活用することも面白みの一つです。
戦後公団仕様で建設された狭い社宅住まいをしていた頃使っていたライティングデスク(写真1)が竹とんぼアトリエです。30代半ば頃に購入したこのデスクは、新商品のアイディア描きに使われ、今は竹とんぼの高性能羽根の捻り出しに酷使され現役バリバリです。
作業が終わればテーブル板を閉め格納するつもりが、雑物置き場となっています。
作業スペースはゴミ受けを兼ねた木箱です。この木箱は大分県の一村一品の贈り物の木箱でした。木箱側壁にスライドレールを着け、その上に作業台を載せています。作業台には、小型万力とゴム板付き削り台が組み込まれます。作業台を左右反転させれば万力作業が出来ます。作業台をひっくり返し、材料・工具類と共にアタッシュケースに収納し持ち運びが出来ます。
こんな廃材を利用した工夫も楽しみの一つです。皆さんそれぞれの作業環境に応じた冶具や工作補助具を工夫しています。
道具や冶具はこのような工夫の積み重ねと、時間という洗練作業の結果今に残されているのでしょうね。100年後のホームセンターには、竹とんぼ専用冶工具のコーナーが設置されるかも知れません。 |