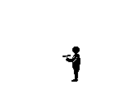ここ暫くは竹とんぼから離れて、よじ登りの「虫」作りに励んでいます。あぜ道で見つけたひなげしや小判草の擬似虫に加え、かるーい紙粘土で虫を作りました。
「てんとう虫」や「カタツムリ」です。てんとう虫に色付けするためインテーネットで色柄の種類を調べてみました。ありました。ニジュウヤホシテントウムシという名の背中には20以上の斑点が付いています。一番多いのが28の星がある仲間で、ジャガイモや茄子の葉を食べる農家の天敵だそうです。
マグネットの磁力の大きさ、虫ピンの頭の大きさ、全体の重さを調整し、よじ登りの途中で落ちない虫を作っています。紙粘土は非常に軽く、大きな形で作っても0.15グラム以下に収まりました。この重量を計測するのに、スーパー竹とんぼ作りに欠かせない0.01グラムまで計れる重量計があるから助かります。
紙粘土を指先で捏ねながら虫の形を想像し、指先に指令を出します。あまり永く捏ねていると乾き、紙の粉が指先から舞い上がります。手短に造形し水をつけて部品をつなげます。
これを見た子供たちのびっくりする笑顔を思い浮かべながらせっせと作ります。
写真1 紙粘土で形を作ります。部品のつなぎは水気を付けま す。
写真2 下塗り、粘土の白色が色を引き立たせます。
写真3 目を付けます。
写真4 色斑点を付けます。最後につやだしニスを2回塗り ます。
斑点は、竹串の先端を平にし、適当な径に削り、白目と黒目、星の丸の大きさにします。絵具を先端に付け、印鑑を押す要領でマーキングしていきます。絵具が薄いと地の色が透けたり、溶け出しますので、適当な濃さ(粘性)が必要です。
目つき、背中の丸み、星の数と色の組合せを愉しんでいます。
60過ぎの親父が何をしてるんだ、と変人扱いにされないようこっそり密やかに愉しんでいるこの頃です。 |