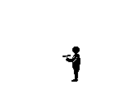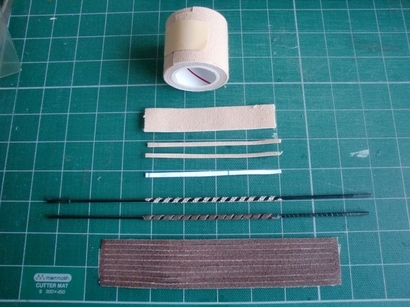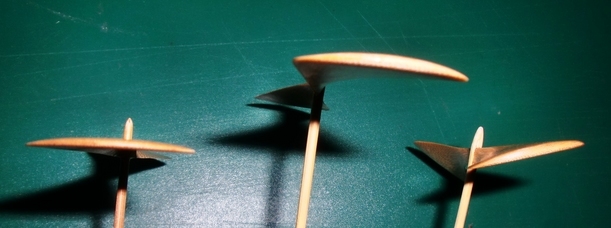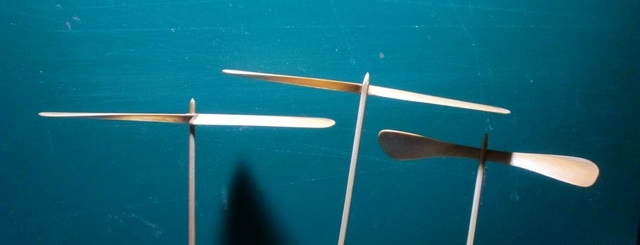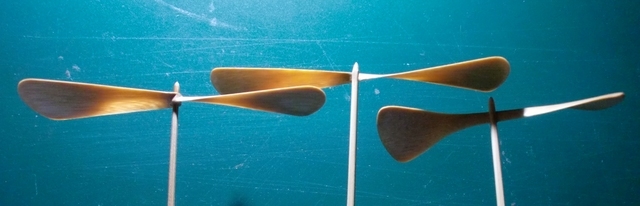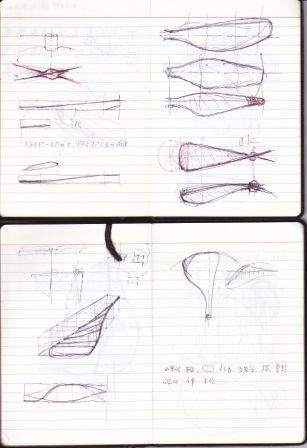|
CATEGORY:竹とんぼとの苦闘
|
2010/10/08 21:09:54|竹とんぼとの苦闘 | ||
仲間からの情報・・・前進面の曲面加工具の発見 | ||
|
2010/09/09 22:36:05|竹とんぼとの苦闘 | ||
仲間の皆さんに教わり競技用を製作 | ||
|
2010/09/08 21:59:17|竹とんぼとの苦闘 | ||
手ごたえのあるトルク感を出す工夫 | ||
|
2010/07/26 21:27:26|竹とんぼとの苦闘 | ||
炎天下での挑戦・・・暑いほど熱い・・・これぞ熱中人 | ||
|
2010/07/06 22:43:16|竹とんぼとの苦闘 | ||
苦悩の記録・・・ポンチ絵の教え・・・技術屋の心眼 | ||
|
[ 1 - 5 件 / 41 件中 ] NEXT >>